『ストーナー』 ジョン・ウィリアムズ 【あらすじ・感想】
初稿:
更新:
- 27 min read -
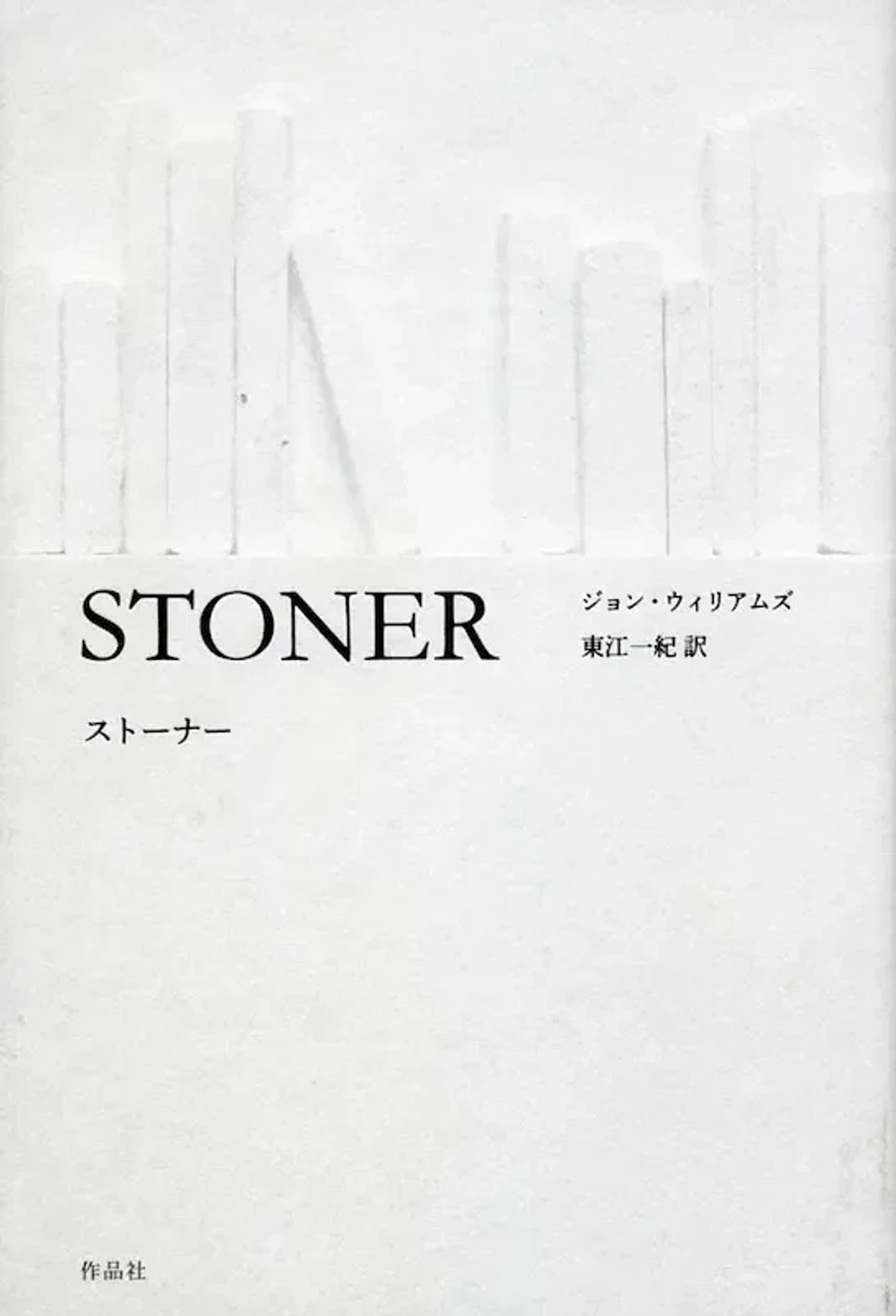
あらすじ
農場で働く両親の元で生まれ教師となり、妻と娘を家族に持ち、病気で死んでいったある男の一生を語る一作。
ウィリアム・ストーナーは、一九一〇年、十九歳でミズーリ大学に入学した。その八年後、第一次世界大戦の末期に博士号を授かり、母校の専任講師の職に就いて、一九五六年に死ぬまで教壇に立ち続けた。終生、助教授より上の地位に昇ることはなく、授業を受けた学生たちの中にも、彼を鮮明に覚えているものはほとんどいなかった。 年長者にとってその名は、諸人を待ち受ける終わりの日の標であり、若者の者たちにとっては、過去のいかなる感覚も、また、自分自身もしくは自分の履歴と響き合ういかなる美質も呼び起こさぬ、単なる音の連なりにすぎない。— 第1章、冒頭より引用
読書感想
本書との出会い
SNSで数多く見かけた熱い思いに突き動かされ、読んでみようと思った。
私は普段、カバーや帯を取り去った状態で本を持ち歩き読書をする。
本書の白く美しいカバーの下には濃い臙脂色の表紙と銀文字のタイトルがある。
読み進むに連れ、表紙の臙脂色はかつてストーナーが生まれ育った農場の土と、そしてタイトルの銀色はストーナーの灰色の瞳と重なっていった。
本書は隅々までが「ウィリアム・ストーナー」という男の人生に満ちている。
本書における見どころ
農家の子として生まれ恩師と文学に出会って教師となり、生涯の友を得て家族を持つ。天敵に最悩み、両親の死と直面し晩年の恋、そして病。
人生に起こる出来事として際立ったものは無く、そこには特別な栄冠もない。
しかし彼は周囲に、あるいは自分の内面に、湧き起こったすべてを静かに受け入れ、人生が悲しみに包まれた時ですら手を抜くことがない。
彼の一生は「人生を生きることはどういうことか」を体現したものであり、生の実感を得る機会が乏しい私にとって、とてつもなく眩いものであった。
彼は人生のさまざまな局面において自分の茶色く節くれだった手を見つめる。
その行為は「自分が何者であるか」を確かめる儀式のようであり、それは人間にとってとても大切なことで、そして忘れやすいことでもある。
生い立ち
ストーナーはミズーリ州の貧しい農家として働く両親の元で生まれ、学校に通う傍ら両親と共に農作業をしながら育った。
高校を卒業し、新設される「ミズーリ大学」農学部に入学する話が持ち上がり進学することとなる。
一年目の成績は、平均でBをやや下回る評価だった。ストーナーはそれ以下でなかったことを喜び、それ以上でなかったことは気にしなかった。 — 本書より引用
口数少ない両親の元で育った彼は言葉で多くを表すことをせず、不器用に与えられたすべてをこなすように努める。
まずストーナーに抱く印象は「凡庸」であり、「忍耐強さ」であった。
恩師、文学との出会い
親戚の元で重労働との両立を要した大学生活だが、そこで人生の転機が訪れる。 それは本業の農学部課程ではなく教養科目、英文学の授業でのことだった。
シェイクスピア氏が三百年の時を越えて、きみに語りかけているのだよ、ストーナー君。聞こえるかね? 氏のソネットは何を意味するのだろう? — 本書より引用
尊大な物腰でほとんどの生徒から嫌われている英文学講師アーチャー・スローン、彼はシェイクスピアの詩を詠じたあと、こうストーナーに問いかける。
この時の出来事が文学への目覚めと青春期における自己認識の機会となり、その後スローンの奨めで教師を目指すことにつながる。
この時は気付かなかったがスローンが詠じたこの七三番の詩はとても重要だ。
このスローンという人物は非常に偏屈ではある。だがその内面は、ある種の無念さを抱えながら文学に目覚めたストーナーへ熱い思いを託そうとする姿が印象的だ。とても魅力的な人物である。
ストーナーが正規の教師として一歩を踏み出す際、スローンはかつてストーナーが文学に目覚めるきっかけとなった上記の講座を割り当てる。
なんという「粋な計らい」であろうか。
また、第一次大戦で多くの学生が自ら戦場に赴こうという機運の中、彼がストーナーにかけた言葉からは深い愛情を感じさせられる。
きみは、自分が何者であるか、何になる道を選んだかを、そして自分のしていることの重要性を、思い出さなくてはならん。人類の営みの中には、武力によるものではない戦争もあり、敗北も勝利もあって、それは歴史書には記録されない。どうするかを決める際に、そのことも念頭においてくれ — 本書より引用
本書を読んだ人の中でスローンファンとなった者はけして少なくないのでは。
友との出会い
学生時代、図書館で本の登場人物たちとの交流が主であったストーナーは、非常勤講師となってはじめて友人を得る。(つまり学生時代、彼は「ぼっち」だった)
デイヴィッド・マスターズ、ゴードン・フィンチ、彼らはストーナーの生涯の友となる。 マスターズの存在は生涯に渡ってストーナーの中で消えることはなく、フィンチもまた付かず離れずストーナーを支えていく。
中でもマスターズの人を見抜く明晰な頭脳とどこか投げやりな雰囲気は印象深い。 彼は大学という存在、そして友人二人のその人となりだけでなく、未来まで見通していたように思う。また悲しい彼自身の近い未来をも。
おれは無責任でいられる場所に、誰にも迷惑をかけない場所に閉じこもる必要があるのさ — 本書より引用
この若い三人が酒場で語らう場面はとても美しい。
彼らの間には青春ドラマのような際立った関わりあいは見られない。
しかしマスターズを中心にそれぞれが思いを巡らせ語らう彼らの姿からは、不確かな自分たちの存在を確かなものにしようとする様子が見て取れるもので、彼らが青春の只中にあることを感じさせられる。
家族との出会い
戦争が終わったあと、ストーナーは突然訪れた春の嵐のように恋をする。 ある歓迎会で出会ったイーディス・エレン・ボスとウィックに対し、不器用かつ真摯に思いを告げる。
家族を持つよい妻になるよう努めます、ウィリアム。わたし、努めます — 本書より引用
彼の思いに対し、イーディスは唐突にこう宣言した。
宣言の言葉からも見てとれるが、イーディスもまた不器用である。
思い込み激しく標的を定め(子作り、子育てすらも)、それに向かって全神経を注ぎ込むことだけが人の務めであるかのような生き様はとても痛々しい。
他者との関わりあいをゆっくりと深めていくことを知らずに家庭を築いていく二人は見ていてとても不憫である。
そんな彼らの間で生まれた娘グレースもまたしかりである。
両親の死
ふたりは今、人生を捧げてきたその土にいだかれ、年々ゆっくりと土に同化していく。ゆっくりと、湿気と腐敗が屍を納めた松材の箱を浸し、ゆっくりと屍そのものに触れ、ゆくゆくはその物理的存在の最後の名残までを食い尽くす。そして、ふたりは遠い昔に身を献じた不屈の大地の名もなき一部となり果てるのだ。 — 本書より引用
やがてストーナーは年老いた両親の死と直面する。
病に倒れた父と、その後父のあとを追うように死んでいった母親を思いストーナーが抱いた死生観は普遍的な悲しみを表す。
原点となる土の匂いを思い出しながらやがて訪れる自分の死に対する静かな覚悟を感じる。
天敵との出会い
ミズーリ大学に赴任して来たホリス・ローマックスは体に障害を持つものの非常に明晰な頭脳を持っており、ストーナーは彼にマスターズの面影を見い出す。
しかし、ある一件で生涯にわたってストーナーを許すまじ相手とみなす。
ローマックスの助手チャールズ・ウォーカーがその原因となる。
ウォーカーの知ったかぶりや調子に乗った振る舞いは目に余るものがあった。
ストーナーは彼にに対し低評価を与え、これを巡ってローマックスと激しく対立したことがその後の確執の原因である。
ここから三度に渡る大戦が勃発する。
- 出世したローマックスはストーナーに対し恣意的な授業の割り当てを行う。(第一次ストーナー・ローマックス大戦)
- ストーナーが学内の講師と恋に落ち、ローマックスは彼らの学外追放を企む。(第ニ次ストーナー・ローマックス大戦)
- 定年延長の権利を持つストーナーに対しローマックスは権利行使を阻止する。(第三次ストーナー・ローマックス大戦)
なぜローマックスはこれほどの執念とも言える気持ちをストーナーに抱いたか。 ローマックスとウォーカーは共に障害を抱えており、これが二人の絆を固くする要因と思われる。
ローマックスにとってストーナーがウォーカーに下した評価は、障害者を排除する行為と写ったのではないか。
これに対しストーナーは、後半の争いはむしろ楽しんですらいる様子もあり、ローマックスに対して抱く気持ちは初期の印象から一貫して変わっていないように思える。
新たな恋との出会い
やがてストーナーは短いながらも真実に満ち溢れた恋をする。 相手はちょうどウォーカーの一件があった頃に知り合ったキャサリン・ドリスコル。
内気で不器用な二人は時間を掛けて互いの距離を縮め、いくつかの誤解を経て結ばれる。
人生四十三年目にして、ウィリアム・ストーナーは、世の人がずっと若い時に学ぶことを学びつつあった。恋し初めた相手は恋し遂げた相手とは違う人間であること。そして、恋は終着点ではなく、ひとりの人間が別の人間を知ろうとするその道筋にあることを。 — 本書より引用
しかし学内で知れ渡りつつあったストーナーの恋は終わりを告げる。
その要因はもちろんローマックス!
傍から見れば許されざる恋ではあったが、後に、二人はこの出会いが必要不可欠であったことをそれぞれが証明する。
ドリスコルは研究の成果を出版し、そこには「W・Sに捧ぐ」の一文が添えられていた。
そしてストーナーは大きな気づきを得るに至る。
情熱の力、愛の力は無感覚と無関心と退避の日常のなかでも昔からずっとあったものでありこれからも決して失うものではないと気づく。それは精神的な情熱でも肉体的な情熱でもなく、両方を包括する力なのだ。この力こそが愛の本質、まさに愛の真髄だ。女性に、詩に、それはただこう告げる。見よ、わたしは生きている! — 本書より引用
病そして死へ
第17章は最終章であり、ストーナーの人生最後のくだりである。 余命を意識したストーナーが周りに向ける目はとても穏やかだ。
死の際において朦朧とする意識のなか彼が見つめるさまざまを読み進めているとき、ふと頭に浮かんだのが冒頭の章でスローンが詠じたソネットである。
かの時節、わたしの中にきみが見るのは
黄色い葉が幾ひら、あるかなきかのさまで
寒さに震える枝先に散り残り、
先日まで鳥たちが歌っていた廃墟の聖歌隊席で揺れるその時。
わたしの中にきみが見るのは、たそがれの
薄明かりが西の空に消え入ったあと
刻一刻と光が暗黒の夜に奪い去られ、
死の同胞である眠りがすべてに休息の封をするその時。
わたしの中にきみが見るのは、余燼の輝きが、
灰と化した若き日の上に横たわり、
死の床でその残り火は燃え尽きるほかなく、
慈しみ育ててくれたものとともに消えゆくその時。
それを見定めたきみの愛はいっそう強いものとなり、
永の別れを告げゆく者を深く愛するだろう— 本書より引用
ここまで読み進めてきたストーナーの一生がこの冒頭の詩と深く深く重なり合う瞬間は、背筋が震えるほど強烈であった。
自分の人生を目覚めさせた詩をその後の人生で体現したかのような彼の生き様に深い感動を覚えた。
唯一自分が残した著書を手もとに開き逝く姿からは穏やかな充足感が伝わってくる。
著者・訳者について
ジョン・ウィリアムズ(John Edward Williams)
1922年8月29日、テキサス州クラークスヴィル生まれ。第二次世界大戦中の1942年に米国陸軍航空軍(のちの空軍)に入隊し、1945年まで中国、ビルマ、インドで任務につく。1948年に初の小説、Nothing But the Nightが、1949年には初の詩集、The BrokenLandscapeが、いずれもスワロープレス社から刊行された。1960年には第2作目の小説、Butcher’sCrossingをマクミラン社から出版。また、デンヴァー大学で文学を専攻し、学士課程と修士課程を修めたのち、ミズーリ大学で博士号を取得した。1954年にデンヴァー大学へ戻り、以降同大学で30年にわたって文学と文章技法の指導にあたる。1963年には特別研究奨学金を受けてオックスフォード大学に留学し、さらにそこでロックフェラー財団の奨学金を得て、イタリアへ研究調査旅行に出かけた。1972年に出版された最後の小説、Augustusは、このときの取材をもとに書かれた作品で、翌年に全米図書賞を受賞した。1994年3月4日、アーカンソー州フェイエットヴィルで逝去。 — 本書より引用
東江一紀(あがりえ・かずき)
1951年生まれ。翻訳家。北海道大学文学部英文科卒業。英米の娯楽小説やノンフィクションを主として翻訳する。訳書に、ピーター・マシーセン『黄泉の河にて』(作品社)、トム・ラックマン『最後の紙面』(日経文芸文庫)、ガウラヴ・スリ&ハートシュ・シン・バル『数学小説確固たる曖昧さ』(草思社)、マイケル・ルイス『世紀の空売り』(文春文庫)、ドン・ウィンズロウ『犬の力』(角川文庫)、リチャード・ノース・パタースン『最後の審判(上・下)』(新潮文庫)、ネルソン・マンデラ『自由への長い道(上・下)』(NHK出版、第33回日本翻訳文化賞受賞)など。また「楡井浩一」名義で、エリック・シュローサー『ファストフードが世界を食いつくす』、ジャレド・ダイアモンド『文明崩壊(上・下)』(以上草思社文庫)、ジョセフ・E・スティグリッツ『世界の99%を貧困にする経済』(峯村利哉との共訳、徳間書店)、トル・ゴタス『なぜ人は走るのか』(筑摩書房)など。総計200冊以上の訳書を残し、2014年6月21日逝去。 — 本書より引用
メモ
キーワード
ミズーリ大学 University of Missouri
The University of Missouri (Mizzou), located in Columbia, educates tomorrow’s leaders and relentlessly pursues solutions for a brighter future.
ジェシー会館 Jesse Hall
好きな箇所の引用
以下本書より引用
ただし、やるんだったら、神のためでも、お国のためでも、親愛なるミズリー大学のためでもなく、あくまできみ自身のためにやれ — P40
戦争は単に、何百、何千の若い命を奪うだけではない。人民の中の、けっして取り戻せない何かを殺してしまう。人民がいくつもの戦争を経験すると、早晩、残るのはただ獣の性根だけ、われわれーーきみやわたしや類を同じくする者たちーーが泥からこしらえ育てた魔物だけということになるだろう — P41
学究の徒は、生涯を賭けて築こうとしてきたものを壊す任を負わされるべきではない — P41
そのみごとな痩せっぷり、餓えっぷり。まさに呪われし者だ — P44
文学が持つ、言語が持つ、頭と心の神秘が持つ愛の力が、黒く冷たい活字からなる文字や単語の偶発的で霊妙で予測もつかない組み合わせの中に姿を現した。今まで不法で危険なもののように内に秘めてきたその愛を、ストーナーは最初はおずおずと、少しずつ大胆に、やがて誇らしく、表に出し始めた。 — P131
自分の人生は生きるに値するものだろうか、値したことがあっただろうか、と自問した。(略)この問いがもたらす悲しみは、ストーナー自身や個人的な運命とはほとんんど関わりのない普遍的な悲しみだ(と思えた)。(略)それは歳月の集積から、宿命的な偶然的な情況から、そしてそういう諸々に対する自分の理解から生じたものだ、とストーナーは確信した。(略)その諦念とは、長い目で見れば、よりどころとなる学識まで含めすべてのものが、はかなく空虚で、いずれは永劫不変の無の中に消えていくというものだった。 — P211
ストーナーは娘が、その言葉通り、絶望に寄り添いながら、幸せに近い生活を送っていることを受け入れた。この先も、年々少しずつ酒量を増やしながら、穏やかな気持ちでがらんどうの人生に沈み込んでいくことだろう。父親として、少なくともグレースがその道にたどり着いたことを喜び、娘が酒を飲めるという事実を寿いだ。 — P293